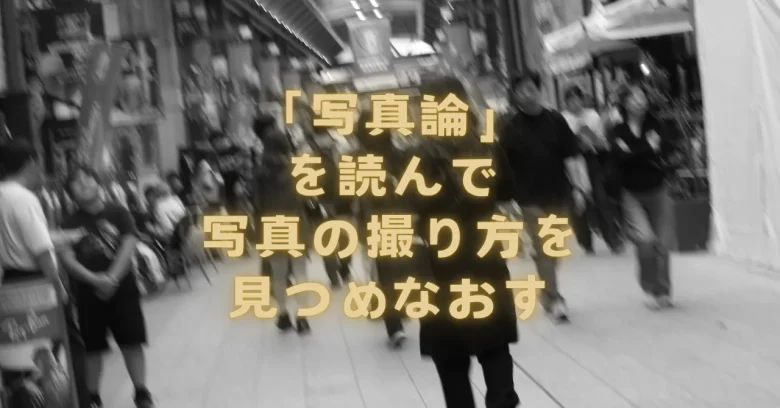皆さんは「写真論」を読まれたことはありますか?
写真を撮るのは好きだけど、思うような一枚が撮れなくて悩むことってありませんか?
私は、それはもう頻繁に陥ります。
写真撮影は、「ただ記録を残すだけ」であれば悩む必要はありませんが、こだわり始めてカメラとレンズを揃えてたくさん写真を撮るうちに、「良い写真を撮りたい」「そしてその”良い写真”とは何か?」と考え込んでしまうときが必ず(とは言い切れませんが)やってきます。
そんなときは『写真論』や『フォトエッセイ』に触れてみることをおすすめします。
読み終わったとき、写真の見方や撮り方が劇的に変わる可能性があるのです。
この記事では、写真論について考察し、初心者の方にも読みやすいおすすめの本をご紹介します。
後半に、私なりの写真論「写真という問いに答えはない!?」も執筆(?)いたしましたので、ぜひご参照ください。

写真論が教える新しい視点
私もたくさんの写真論、フォトエッセイを読んできました。
著名な写真家や評論家など、それぞれ写真に対する深い哲学や考え方が存在することが分かります。
写真への理解を深め、もっと魅力的な一枚を撮るためのヒントを探っていきましょう!
そもそも写真論とは何か?
写真を趣味として楽しむ中で、ふと「撮る写真にもっと個性があれば」と感じたことがあると思います。
…と、勝手に決めつけてはいけないですが、まさに私自身がそうなのです。
大した写真を撮ってもいないのに?と思われるかもしれませんが、本当に撮影目的で訪れた場所で、ほとんどシャッターを切れないこともあれば、数か月カメラを持たないということも、何度でもありました。
そんなとき、私はカメラを本に変えて『写真論』にその答えを求め彷徨います。
写真論とは、写真を単なる技術的なスキルではなく、芸術として、あるいは社会的な表現を伝える手段として捉えるなどして、著名な写真家や評論家が、自らの写真についての考えや思いを語りつくすエッセイのようなものです。
そういった書籍は、読む人に写真への新しい見方をもたらしてくれます。
例えば、何気ない日常のスナップ写真でも、何気なく撮るのではなく、その街の背景にある文化や歴史、物語を意識しながら撮影することで、より深みのある写真に仕上げることができます。大げさかもしれませんが、そういった視点を持ち、学ぶことで、撮影そのものが一段と深く・楽しくなる可能性が出てくるのです。
 フォトあ
フォトあ一人で悶々と撮っていては気づけない視点ですね



そこまで意味を考えて撮る人がどのくらいいるのか疑問ですね
見えないものを写す力
「この写真を見た人に何を感じてほしいか?」—いろいろな写真論を読んでいると、このように考える習慣が少しずつ身についてきます。単に”美しい風景”を見たままに撮るだけでなく、その場の雰囲気や感情を写し取る力も養われてきます。
例えば撮影するときに、被写体の位置だけでなく、光の射し込む角度や陰影の強弱を活用することで、感動や緊張感を伝えられるか?みたいなことを意識できるようになるかもしれません。
※ところどころ作例を載せますが、そのテーマで写真が撮れた!といっているわけではありません🙇
日常風景に込める哲学
写真を深く見つめ直すと、同じ風景ですら視点を変えることで新しい魅力を発見できるようになります。
いつもの景色も、時間帯や天候により全く違う雰囲気になりますし、見慣れた道でも、雨上がりの舗道に映る街灯の反射を意識する。毎日過ごす自分の部屋ですら、窓越しに差し込む淡い朝の光を狙って撮りたくなったりします。
普通のことかもしれませんが、写真論を通じて、こうした一瞬一瞬をより「特別な感覚」を持って切り取る力が育まれるかもしれません。
なんでもない日常をもっと豊かに感じ取れるようになる。
美しい山、美しい花、観光地、映えスポットに行かなくても、今目の前の景色に価値を見出す。
それだけが目標ではありませんが、そういった気づきが写真論を読み解くことの魅力のひとつです。
おすすめの写真論
ここからは、おすすめの写真論を紹介してまいります。
非常に個人的ではありますが、感銘を受けた・読み応えがあった著書を紹介させていただきます。
マイナーな著書もありますので、書店等でも見つけにくいかもしれない点、ご了承ください。
『彼らが写真を手にした切実さを』大竹昭子 著
この本は、作家であり写真評論家でもある大竹昭子氏が2011年に発表した、「”日本”写真」について深く追求した著書です。
森山大道、中平卓馬、荒木経惟、篠山紀信、佐内正史、藤代冥砂、長島有里枝、蜷川実花、大橋仁、ホンマタカシ
そうそうたる現代の写真家10人と実際に接し、感じたことを簡潔にまとめています。
大きなポイントは、外国にはない日本人の感性から「日本独自の写真」があることに焦点を絞っていることです。
写真について語る著書は、たいてい「写真とは」が主語なのですが、こちらの著書は「日本の写真とは」がテーマです。
普通に考えれば、国が違えば人種は異なりますし、気候も言語も食べ物も習慣も全く違うので「写真」に対する考え方も異なるのは当然のことではありますが、ここまで日本人に特化して、具体的に言及した著書はほかにないかと思います。
著者の大竹さんは、90年代に「目の狩人」という本を出版しているのですが、そこからの再構成と、2011年当時に取材した内容を足してこの本を新たに出版した、とのことです。
『写真はわからない』小林紀晴 著
この本は、写真家・小林紀晴氏がプロとしての経験や視点から写真について考察している、興味深い一冊です。
タイトルの通り、写真を「わからないもの」として語り、結論もそのまま「わからない」、けど面白いのが写真である、と述べています。
私のような一生素人の写真愛好家が言うのはお門違いですが、私も同じように思っています。
紀晴氏は、この本の執筆を始めて発行に至るまで、実に10年かかったとのことです。つまり、それくらい「写真とは〇〇だ」とは言えないし、分からない理由を伝えるのは難しいということかもしれません。
プロの写真家がそのように結論を出しているのですから、私たちも「わからない」ということを前提に、言い換えれば分かろうとせず・答えを決めつけず、いつまでも自分が楽しく面白く、興味の持てる被写体を撮ることが長く続ける秘訣なのかな、と思います。
『なぜ上手い写真が撮れないのか』丹野清志 著
こちらも著者は写真家、丹野清志氏の書籍です。
写真論というよりは、写真撮影の極意に近いかもしれませんが、丹野さんの本はとても分かりやすくて私は何冊か拝読しております。
何というか、「プロとして上から教える」というより素人の目線に立ってくれている感じの文章なのです。
写真撮影を趣味にして、のめり込んでいくほどに様々な情報が気になってしまい、何をどのように参考にしたらよいのか分からなくなってしまうことがあると思います。
ちょっと上級者の人に「へぇ…そんな写真撮ってるんだ…」みたいな含みを持った言い方をされると「えっダメなの?」と不安になったり、自信を無くしたりするものです。
しかし、丹野さんは教室で習うような写真の撮り方を守るようなことはおすすめせず、固定観念に囚われすぎて可能性を狭めるようなことにもならないよう、優しく語りかけてくれます。
悩んだときに読めば、頭の中がリセットされて、もう一度新しい気持ちで撮影に取り組める…そんな一冊です。
写真論はたくさんある!
他にもプロ写真家や評論家が、写真について語っている本はたくさんあります。
荒木経惟、ホンマタカシ、森山大道など、多くの巨匠たちが、たくさんのヒントをくれています。
あれもこれも、と読み過ぎると良くないかもしれませんが、「撮影テクニック本」ばかり読まれている方は、ときどき「文字」から写真の何たるかを紐解いてみるのもいいものです。
個人的には、昭和の巨匠・木村伊兵衛のエッセイ本「僕とライカ」のような、カメラの原点から撮り続けた写真家の本もかなり好きです。デジタル以前の、写真というものの価値が今とは全く違う世界の話を読んでいると、タイムスリップしているような感覚に陥ります。
さらに昔に遡って福原信三・福原路草兄弟の写真集「光と其の階調」にある福原信三語録「良い写真の考え方」も、非常に勉強になります。
例に挙げたのはほんの一部で、まだまだまだたくさんの貴重な書籍が存在します。
最近のプロ達の言葉や考え方だけではなく、何十年も前の大物がどのように考えていたかを知ることも、写真に対する思いを深くするのに非常に意味があります。
写真論で変わる実践的テクニック
構図の再発見
写真を本格的に学び始めると、まずは「黄金比」や「三分割法」などの基本的な構図を覚えていくのが必然です。しかしそれらを覚えて守るだけでは、面白みを見失い、じきに限界を迎えてしまいます。そんなときに写真論を読んでみると、そういった構図の知識を超えて、写真が持つ「物語性」のようなものを追求し、撮影していくことが大切だと分かっていきます。
例えば、主役をあえてギリギリ画面の端のほうに配置し、空間の「余白」を大きくすることで、観る人に想像の余地を与えるといった感じでしょうか。
覚えた構図や撮影テクニックに捉われすぎないことは大切です。
撮影したときの感情や、場所が醸し出す物語性を頭の片隅に少しでも意識することで、思いもよらない配置にピンと来て自然とシャッターを押す。そのとき、ハッキリと自覚できるような”傑作”が生まれるかもしれません。
光と影の重要性
写真における光と影の使い方は、作品の印象を大きく左右します。様々な写真論で、自然光や人工光、それに対する影をしっかりと生かすことが大切と書かれています。これは、写真そのものに「語りかける力」を与えることに繋がっていく、といっても過言ではありません。
例えば、斜めから差し込む朝の光を被写体と組み合わせれば、写真全体に柔らかな立体感を与えることができます。また、影を大胆に取り入れることで、より意味ありげな雰囲気を表現することも可能です。
いつもの平凡な風景を、少し時間帯を変えて撮影してみてはいかがでしょうか。
こんなところでこんな写真が?みたいな、驚きの発見があるかもしれません!
色彩と感情の結びつき
「色」は、写真論でも重要な要素として語られます。
色には、それぞれ特有の感情を引き出す力があります。赤は情熱やエネルギーを表し、青は静けさや安らぎを象徴します。この色彩が持つ心理的効果を意識することで、観る人の感情をより強く引きつける写真を撮ることができると、多くの写真家が伝えています。例えば、夕焼けの赤とオレンジを強調することで、暖かさや懐かしさを表現する写真が撮れるのは想像がつくと思いますが、被写体や撮る場所によって、見る人に異なる印象を与えることができたりします。曖昧な言い方をしてしまいましたが、要はオリジナリティーを追求しよう、ということになるのです。
撮りたいと思う写真を撮ろう
一番よくある見解でもあり、一番大切なことは、撮りたい写真を撮りましょう、です。
楽しい・面白い・興味深いなど、自分が撮りたいものを撮らないと、恐らく長続きしません。
当たり前じゃないか!と思われるかもしれませんが、カメラ・レンズの設定や基本の構図など、知識がある程度ついてくると、それらを意識し過ぎて「教科書的な良い写真を撮らなければ」みたいな思いに憑りつかれるときが、そのうちきっと、やってくるのです。
例えば、電車に興味がないのに「鉄道撮影テクニック」を読み、設定に従い撮影し、「おぉ上手く撮れた!」となったとしても、電車を撮りたい気持ちが本物でなければ続けるのは難しいでしょう。
ということで、根本にある「撮りたいものを楽しく撮る」だけは守り続けることが大切だと思います。
写真論を学ぶべき理由とは?
写真の価値が広がる
写真論に触れることは、趣味としての写真を次のステージに引き上げるきっかけにもなります。写真に哲学や文化的背景を持たせることで、ただの「記録」から「表現」へと変化してゆくためです。
例えば、歴史的建築物を撮る際、建物全体を漠然と捉えるのではなく誰も目を向けないような一角を切り取ったりすることで、その背後にある物語を連想させるような手法が身に付いたりします。
こういった表現力を身につけることで、より魅力的な作品を生み出すことが可能になっていくでしょう。
自己表現の手段として
写真は、言葉では表現しきれない感情や思いを伝える強力な手段です。写真論を学ぶことで、自分自身の「内なる声」を写真というカタチで具現化する方法のヒントを得ることができます。例えば、何気ない日常の風景を撮る際でも、ただ漠然と撮るのではなく、自分だけの視点やそのときの思いを込めた一枚を生み出すことができるようになります。
社会的・文化的つながりの理解
写真は、人々や文化、歴史をつなぐ架け橋としての役割も果たします。普通に撮っていると気づけないですが、写真論を通じて、プロ写真家・評論家の視点や、写真の社会的背景を理解する力もついてきます。
例えば、異なる文化圏の人々の暮らしを撮影した写真集などがありますが、何も知らずにページをめくるより、写真論で知識を得てから見たほうが良いです。
そうすると自分自身も、社会的な共感を得られるような作品を生み出せるようになるかもしれないのです。
結論
写真をもっと楽しむための方法として、「写真論」を学ぶことをおすすめしてまいりました。
それは、視点を広げ、感性を深め、そして写真を通じて自己表現をより豊かにするきっかけとなります。本記事で紹介した名著を手に取り、ぜひ写真の新たな可能性を見つけてみてください。
私の”ざっくり”写真論「写真というものに答えはない」
プロでもない、写真を極めてもいない私があらゆる写真論を読み進めたことで得た結論は、「写真に答えはない」です。
「写真はわからないものだ」などと、素人に産毛が生えたようなレベルの私が口にしたところで「でしょうね」と言われるのが関の山ですが、小林紀晴さんほどのプロでもその結論に至るとは、本当に奥が深いのだと思います。
写真は、この世の全てが「被写体」であり、過ぎてゆく時間の全てが「シャッターチャンス」なのです。
座っている椅子も目の前の机も、家族もペットも、空も海も山も、朝も昼も夜も、いつでもどこでも何もかも被写体なのです。
つまり、「生きていることとは?」といった問いにひとつの答えが無いのと同じで、写真にも答えなど無いのではないでしょうか。
それでも、たくさんの著名な写真家の方々が「写真とは〇〇である」と答えを出されていますが、そこには経験に裏打ちされたそれぞれの写真に対する主観が大きく影響しています。まさに人生経験から導き出されたものです。
当然、写真撮影の経験も乏しいうちに、大好きな写真家の結論を最初から撮影の答えとして持つことは非常に危険です。「先生はこんなもの撮らない!」といった感じで、撮りたいものが撮れなくなる可能性があるからです。
歌の世界であれば、ロックが好きなのに、「歌といえば演歌だよ」という人に丸々合わせることはしないですよね。
カレーだって「甘口が最高だ!」と言っている人に「辛口に決まってるだろう」と主張しても無意味です。
それでも、写真に対する答えはなくても「良い」とされる写真は確実に存在します。
風景写真、家族写真、人物写真…それぞれのジャンルで高く評価される写真家が存在するのですから。
ところが、高く評価された写真が万人にウケるかというと、そうではありません。演歌の巨匠の大ヒット曲を日本人全員が大好き!とはならないことと同じで、好き・嫌いは人それぞれで違います。
その「好き」「素晴らしい」「最高だ」という割合が高くなると「良い」という評価に結びついていくわけですね。
ただし、評価された写真を真似してみても、「似てるね」で終わってしまいます。
「二番煎じ」という言葉があるくらいですから、一番には敵わないということです。
だとしたら、斬新な切り口であったり、独自性があったりすることが評価につながるのではないでしょうか。
そうなると、それはまだこの世にない写真なので、やっぱり「答え」は無いといえるのです(笑)。
・・・長々と禅問答のような文章になってしまいましたが、ご容赦ください。
それくらい、写真が奥深いものだということが伝われば、この上ない喜びです。
この記事から、というより皆様も「写真論」「フォトエッセイ」に触れて、自分が持っていない「写真についての考え方」を吸収してみてください。
本当にとりとめのない記事を最後までお読みいただき、ありがとうございました。