皆さんは「超望遠レンズは不要」と思われますか?
結論としては、必要とまでは言いませんが、”一本くらい”は持っておくことをおすすめします。
主に、遠く離れた被写体を鮮明に・大きく捉えることができる超望遠レンズは、写真を撮る楽しみが増えるアイテムといえるのです。
“良い写真”を撮るために「レンズ選び」は作品のクオリティに直結する重要なポイントですが、本記事ではその中でも超望遠レンズにスポットライトを当て、魅力と実用性、そしてその選び方について「実写レビュー」を交えて紹介させていただきます。
あなたの写真に新しいに息吹を吹き込むこと間違いなし…です!
超望遠レンズとは?
超望遠レンズの基本概念
そもそも”超”望遠レンズとは、焦点距離が300mm以上のレンズを指します。
遠くの被写体を大きく捉えることができるため、遠くにいる被写体…スポーツであれば選手、また自然風景では鳥などの野生動物を、遠距離撮影が求められるシーンで力を発揮します。
超望遠レンズの主な用途
超望遠レンズは、スポーツ、野鳥観察、風景など、幅広いシチュエーションで重宝します。当たり前ですが、遠方の被写体に近づけない場面や、大きく捉えたい場面で大活躍します。スポーツ新聞で、サッカー選手とか、競馬で走り抜ける馬の姿など、迫力ある写真を想像していただければ分かりやすいかと思います。
それだけでなく、最短撮影距離を生かして被写体と背景の間にしっかりと距離を置けば、豊かなボケを引き出すこともできます。
超望遠レンズの種類と特徴
各メーカーから様々な種類の超望遠レンズがピンからキリまで、長年にわたり発売されています。焦点距離や絞り値、手振れ補正機能など、それぞれの特徴を把握することで、目的に合ったレンズを選ぶことができます。
その中でも「絞り値」はポイントで、やはりF値が小さいほど、価格も跳ね上がります。また最近のミラーレス用のものは、標準的なスペックでも高額なものが多いです。
できるだけお金を掛けずに写真を楽しむという、本ブログのコンセプトに合わせるのであれば、ミラーレスではなく「デジタル一眼レフ用」の、90年代前後のサードパーティー製レンズを狙います。
うまく探せば、数千円で超望遠レンズを入手できます。
安い分、手ブレ補正機能がなかったり、絞り最大開放値が大きく「暗いレンズ」になってしまいますが、撮影方法を工夫することで「いい感じ」の写真を撮影することができます。
超望遠レンズが要らないと言われる理由4点。
私自身、カメラを始めてからしばらくは「超望遠レンズを買おう」という発想すらなかったので、そもそも一般的な存在ではないのかもしれませんが、鉄道や野鳥、スポーツなどの撮影では確実に重宝します。
なぜ要らないという判断になるのか、理由を4点挙げてみました。
デジタル技術の進化
まずは、なんといってもデジタル技術の向上ですよね。カメラのセンサー解像度が短期間で劇的に向上してゆく時代となりました。
画像を大胆にトリミングしてもある程度の品質を保つことができるようになってきました。
デジタルズームも進化しています。レンズの力による「光学ズーム」と異なり、「画像側」を拡大するため、どうしても画質は粗くなるのですが、大きなプリントでもパソコンでもなく「スマホの画面」で見ることが主流となった今、そこまで気にする必要はなくなりました。
こういった理由から、わざわざ被写体に大接近するレンズを持たなくても、”シャープ”な写真を生み出すことが可能になっています。
重い+大きい=持ち運びが大変
超望遠レンズは、重さも大きさもかなりのもの。それを持ち歩くのは一苦労ですよね。特に遠出する旅行や長時間の撮影では、軽量のレンズや機材のほうが体力的にも助かります。機材が軽ければフットワークも軽くなり、楽しく撮影できるでしょう。
重ければ手持ち撮影も厳しくなり、三脚も持参となると…これ以上言う必要はありませんね(笑)。
こちらの「SIGMA AF-TELE 400mm F5.6」は、単焦点でこのサイズです。

しかもカメラはフルサイズのデジタル一眼レフ「SONY α900」なので、双方でかなりの大きさ&重さです。
レンズに備え付けのフードを伸ばした状態なので、長さも”超一流”ですよね…
撮影に行くとき、このレンズと標準レンズと広角レンズと…なんて想像すると、持ち出すのに躊躇すると思います。
基本的に高額である
超望遠レンズは、開発に掛かる費用や、需要が限定的であるためか、大半のレンズがかなり高額です。
そして、デジタル技術の進化により、高価な超望遠レンズがなくてもトリミングやデジタルズーム、加工などで写真そのものの作り方が変わってきています。
高価な超望遠レンズより、標準的なレンズとか別のアクセサリーに費やしたほうがいい、という判断になってもおかしくありません。
そもそも超望遠で撮る必要がない
基本的に超望遠レンズは「遠くのものを大きく撮ること」が主な目的です。
なので、撮影できる範囲が非常に狭いことから、利便性には欠けると言えます。
その辺のものを撮りたくなったときに、いちいちレンズを交換しなければならないのは非常に手間と言えるでしょう。
そもそも、そんなに遠くの被写体を大きく撮り続けることがあるか?というと、やはり通常の撮影では「要らない」という結論に至るのも、うなずけます。
 プリン
プリンうん、「いらない」で決まり!



いやいや、結論出すの早いから💦
超望遠レンズの魅力
ここからは、逆に「あったほうがいい」と思う理由を作例とともにお伝えしますので、もう少しお付き合いのほど。
実際に私が所有しているレンズを紹介させていただきながら、実写レビューを交えて解説してまいります。
ただし、私が持っているレンズは、かなり古いうえに中古市場でも出回っている数が少なめですので、同じものを探して入手しようとする必要はありません。
※「見つからない」という言い方が正しいかもしれません😅
作例からは、焦点距離のイメージを掴んでいただければよいかと思います。基本的な設定ですが、絞り値は開放で、シャッタースピードはオート。露出補正は±0となっています。
フルサイズ機+400mmレンズ
超望遠レンズの最大の魅力は、その撮影距離なのですが、カメラのイメージセンサーの違いにより「写る範囲」が違ってきます。一般的にイメージセンサーは「フルサイズ⇔APS-C⇔マイクロフォーサーズ」の3種類に分かれます。
どのレンズにも言えることではありますが、望遠レンズとなると特に大きく影響します。
まずは、フルサイズ機+「単焦点の超望遠レンズ」の作例から紹介します。
先ほど画像で登場した、フルサイズのデジタル一眼レフカメラ「SONY α900」&「SIGMA AF-TELE 400mm F5.6」のコンビで撮影しました。
ロケ地は名古屋港です。名古屋市水族館の南にある護岸にいたカモメたち。距離は、体感なのですが10メートル以上離れていたと思います。そこそこ鮮明に撮れている感じですね。
手前の2羽のカモメが「前ボケ」しています。このレンズは決して明るいレンズではないのですが、望遠レンズのボケやすさがお分かりいただけるのではないでしょうか。
こちらは、同じく水族館周辺の風景です。
近景に対して、対岸の建物や橋が近くに見える、いわゆる「圧縮効果」が感じられますね。実際に景色がギュッと圧縮されているわけではないのですが、画角の狭さから「圧縮されたように見える」という話です。
こちらは…「葉牡丹」で合ってますでしょうか?これで2メートルくらいの距離だったはず。
すぐ後ろがしっかりボケているのがお分かりいただけるでしょうか。
あまり寄れないし、絞りも明るくないレンズが多いですが、近くの被写体でも背景をうまく配置すれば、ぱっと見「明るい標準の単焦点レンズ」で撮ったような写真に仕上がります。
次の項は「APS-C機」の作例紹介です。
APS-C機+400mm=600mm?
超望遠レンズは、APS-C機やマイクロフォーサーズで撮影すると、疑似的に”より超望遠化”できます。APS-C機に先ほどと同じ400mmのレンズを付けて撮影すると「フルサイズ機で600mmのレンズを使用するのと同等の画角」となります。これを「フルサイズ換算」と言います。
以下、「SONY α200」で、沖を飛び交う鳥たちを撮影してみました。
鳥が近くを飛んでいるように見えますが、数十メートルは離れています。
こちらもかなり高い橋の上から撮影した、(恐らく)ウミウです。


そして飛び立ったウミウ。逆光で、波に反射する太陽光が宝石のようですね。


余談ですが、光の周囲が青みがかってるのは「パープルフリンジ」といって、レンズの色収差のひとつです。
当然、実際に肉眼で見える波の反射はこのような色をしておりません。
激安で手に入れた中古レンズだから仕方ないか、と思っていたら「仕様」でした。
「シグマ公式サイト」でこのレンズを紹介している記事がありました。シグマ社の大曽根氏によると、開発当時に格安で販売することを優先し、色収差をある程度容認したとのことです。


今回、波の反射を撮影するまではほとんど意識しておりませんでした。
このコンセプト・企業努力のお陰様で今、私はお安く入手できたのですね(笑)。
標準レンズでは味わえない独特の表現力
このように超望遠レンズは、遠くの鳥を大きく捉えるだけではなく、圧縮効果を利用した独特の表現力を実感することができます。
ここまでの作例は、いずれもシグマの「APO TELE MACRO 400mm F5.6」という単焦点の超望遠レンズでした。
このレンズは発売当時も「手に入れやすい超望遠単焦点レンズ」だったそうで、中古相場でも格安です。全く同じ商品でなくてもよいので、ぜひ中古市場で探してみてください👀
便利さを優先するならズームレンズ
400mmの単焦点レンズなんて不便過ぎる…という場合は、ズームレンズがおすすめです。
ここからは「COSINA AF 100-400mm f4.5-6.7 MC」の作例を紹介いたします。
せっかくのズームレンズですが、作例は全て400mmのものです。
…そしてこのレンズは、もっとマイナーなので中古市場でも滅多に見かけません。
池のボートと向こう岸の林ですが、圧縮効果により距離感が掴みづらい、不思議な写真になっています。
こちらは木彫りの馬のシルエット。色滲みが出てますが、背景がボケてちょっと幻想的?な雰囲気です。
木の茂みから覗き見しているような観覧車。かなり遠いですが、引き寄せられているように近く感じます。
アルパカのドアップ。あまり評価の高くないレンズですが、そこそこ鮮明な描写力を見せてくれます。
…これらの作例で「超望遠レンズの魅力」が伝えられたか?というと難しいところですが、最新のカメラと最新の超望遠レンズを用いた、プロの方やハイアマチュアの方の作例を検索してみてください。
本ブログは「お金をかけずに写真を楽しむ」がコンセプトなので、古いカメラ・古いレンズがメインとなっており、高解像度ではない写真が多いです。そのあたりは期待されないよう、お願いいたします🙇



…何か言い訳がましいよね💧
こちらのレンズについて特化した記事をUPしておりますので、ぜひご一読ください!


超望遠レンズの選び方
自分の撮影スタイルや用途に応じて、最適な焦点距離を選びましょう。スポーツや野生動物撮影には、400mm以上のレンズを使うと「超望遠のありがたさ」を実感できます。
例えば、野鳥撮影で「500mm以上」のレンズを使用すれば、感動的な写真が撮れると思います。美しいカワセミを捉えた作品は、このあたりの焦点距離を使用しているはずです。
イメージセンサーのサイズに注意!
このような「焦点距離」の話をするとき、私は必ずイメージセンサーに触れます。
「フルサイズ」とか「APS-C」という言葉を皆さんもお聞きになったことがあるかと思いますが、イメージセンサーの種類によって、同じレンズでも「写る範囲」が違ってくるのです。
400mmの望遠レンズとは、「フルサイズのカメラ」を使用したときの焦点距離となります。
もし、お手元のカメラが「APS-C機」だったら、「フルサイズ換算」をして、1.5倍で計算しましょう。
- 300mmのレンズは、1.5倍で「450mm」※キヤノンは「480mm」
- 400mmのレンズは、1.5倍で「600mm」※キヤノンは「640mm」
- 500mmのレンズは、1.5倍で「750mm」※キヤノンは「800mm」
実際はトリミングなのですが、レンズに記載されている焦点距離より「望遠寄りになる」ことを覚えておいてください!
絞り値と明るさについて
「f2.8」など、開放絞り値が小さい=明るいレンズは、暗い場所や高速シャッターが必要なシーンで有利ですが、望遠レンズになるほど開放絞り値は大きく=暗くなります。超望遠で明るいレンズもありますが、価格も超高額となり、ちょっと使ってみようというレベルでは手が出せません(私の場合)。
また、明るいほどボケが強くなるのですが、望遠の場合は暗いレンズでも、被写体と背景の距離がしっかりあれば、しっかりボケてくれます。
それに、カメラは新しければ新しいほど、ISO感度を上げても、そこまでノイズが気にならないレベルになってきているので、暗いレンズでもカメラの力を借りれば十分に使えます。
手ブレ補正機能の確認
手ブレ補正機能があるかどうかもレンズ選びの重要なポイントですが、古いレンズ、中古で安く出回っているレンズなどは基本的に手振れ補正機能がありません。
カメラ本体にあればよいのですが、どちらにもなければ「自分でブレないようにがんばる」しかないです…
特に、長時間の手持ち撮影は厳しくなるので、三脚も持ってお出かけすることをおすすめします。
前述のとおり「要らない理由」のひとつではありますが💧
手ブレ補正機能は、手持ちで遠景を撮影する際のブレも防いでくれるので重宝しますが、昔の写真家は腕ひとつで毛傑作を生み出してきたのです。
三脚がなければ構え方や、壁に体を当てるなどの工夫により、乗り切りましょう!
価格帯とコストパフォーマンス
超望遠レンズもピンからキリまで、と書きましたが本当に凄まじい価格差です。
今回の記事で使用したレンズは初心者向けのエントリーモデルと言えるでしょう。
プロ仕様の超望遠レンズは、本当に高額です。
作例の「100-400mm」のズームレンズは中古市場で数千円で見つかりますが、キヤノンのいわゆる白レンズ「EF100-400mm F4.5-5.6L IS USM」は中古でも10万円は軽く超えてしまいます。
超望遠レンズに限った話ではありませんが、ときどき使うためなら、とりあえずはお手頃価格のレンズを。本格的・日常的に使うなら思い切ってプロ向けの高級レンズを、と言った感じで、目的に合ったレンズを選ぶのがよいかと思います。
結論
超望遠レンズは、遠距離撮影を劇的に変える強力なツールであることをお伝えしてまいりました。
その驚異的な撮影距離がもたらす独特の表現力は、他のレンズでは味わえない魅力です。用途に応じた最適なレンズを選ぶことで、写真のクオリティを大きく引き上げることができるはずです。
超望遠レンズを”一本”手に入れて、ぜひ新たな撮影体験を楽しんでみてください。
今回の作例で使用したカメラ「SONY α900」は、別の記事でも紹介していますので、ぜひご一読ください!
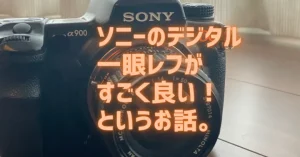
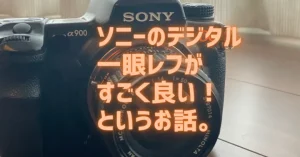
最後までご覧いただき、ありがとうございました。












